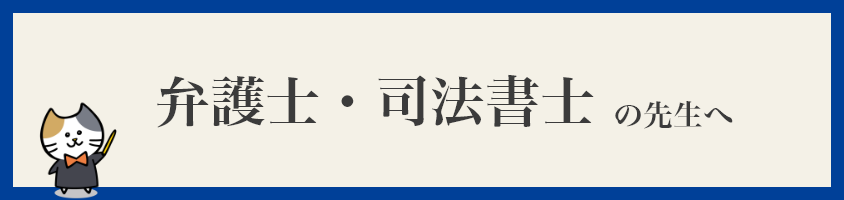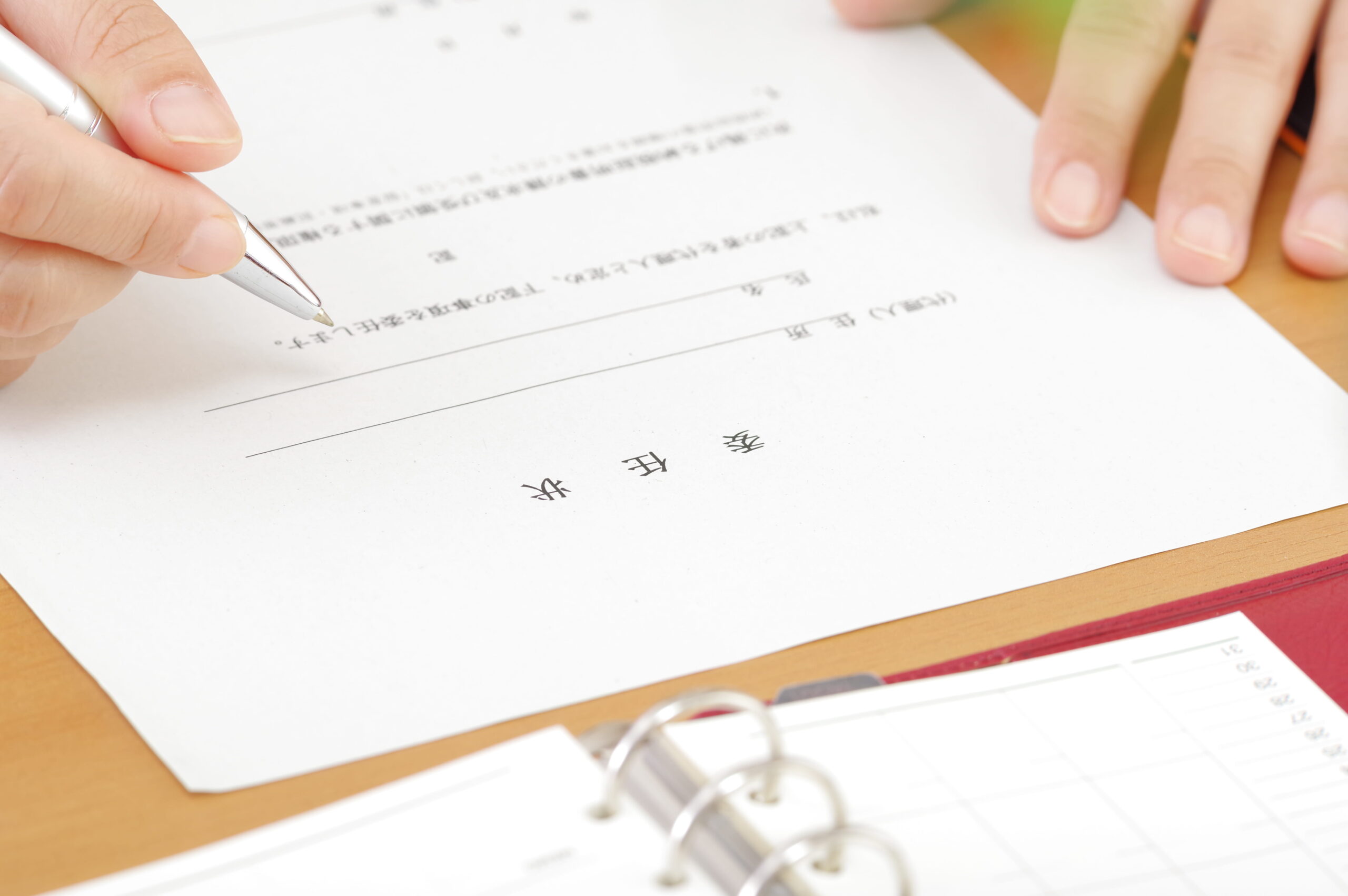株式会社は、何らかの理由によって、解散することもあります。主な理由としては、経営状況の悪化や事業の再編成などがありますが、決して赤字経営が解散事由となることばかりではありません。
今回は、株式会社の解散事由として主な例となる6つのケースについて詳しく解説していきます。
存続期間の満了による解散
株式会社は設立する際に、「定款」(ていかん)と呼ばれる規約を作ります。簡単にいってしまうと、社内のルールを定めるものです。
この定款の中には、会社の存続期間を定めるものが含まれていることがあります。例えば、実在するキャラクターライセンスの事業を行っている企業において、存続期間が100年間と定められているケースがあります。この場合、この株式会社は、設立から100年経つと自動的に解散することが定められているのです。
当然、存続期間を迎える前に以下のような別の理由が発生した時点でも解散となります。
定款にて定められた解散事由の発生
株式会社は、万が一のため、定款にて解散事由を予め決めておくことができます。例えば、会社の業績が振るわず、赤字経営が続いた場合など、具体的な解散事由が定款に明記してあるケースもあります。
このような解散事由がある場合、解散事由が発生した段階で、株主総会の決議を待たずに解散することができます。
株主総会の決議
株式会社の解散は、一般的に株主総会の決議によって決まります。この決議は、「特別決議」と呼ばれるもので、解散が認められるには、出席している株主の議決権のうち、過半数以上が必要になります。
解散を決議する理由としては、経営状況の悪化や事業内容の変更、方針の転換など、さまざまです。
合併する場合
よくニュースとかでも耳にする「合併」は、他の会社と合併することによって、現在の株式会社としての形が消滅する場合を指しています。合併の場合は、解散する(消滅する)株式会社と、吸収合併という形で存続する株式会社との間で、”合併契約”というものを締結することとなります。
また、この場合は、解散して存続できなくなった会社の株主に対して、適正な払い戻しや株式交換などの処理手続きも行われるため、清算手続きは不要です。
破産手続開始の決定
株式会社が解散する事由として多いのは、財政状況の悪化です。とくに近年は、感染症流行の影響を受けて、破産の手続きをせざるを得なくなった企業も多くあるのではないでしょうか。
借入金の返済が難しくなった場合には、債権者に適正な配当を行い、同時に会社を解散させるため、破産手続きをとります。手続きの開始が決定された時点で、解散と同等になります。
破産手続きの中には、清算手続きも含まれます。
解散を命ずる裁判
株式会社が何らかの法律に触れた場合、公序良俗違反と判断された場合などは、裁判所から、解散を命ずる決定を受けることもあります。これは、重大な問題が生じた場合にのみ出されるものです。
裁判所側は、解散命令を出すにあたって、株主や債権者の利益などを考慮しつつ、決定を下します。
定款(ていかん)に解散事由を含める利点
株式会社の解散事由を定款に定めることは、以下のような目的、メリットがあります。
解散事由の明確化
解散する理由が明確に定められている場合、解散する時期や解散に対する対応、手続きをスピーディーに済ませることができるため、問題の早期解決が図れ、予測外の解散を免れることができます。
株主の保護
解散事由を定めることによって、株主も、解散事由を把握することができます。また、会社の経営に対して疑問が生じた場合にも、株主は解散事由に沿って考えることができるため、株主保護の1つとしても大切なポイントです。
合理的な解散
解散の時期の見極め、破産手続きの開始など、全体を把握しやすく、適切に問題を解決することができます。
また、解散事由に当てはまらないように、事前に対応することも可能であるため、結果的に株式会社の損害を未然に抑えることにも繋がります。
法的効力がある
定款の中に解散事由が定められており、その事由が生じた際は、株主総会の決議(特別決議)を行わなくとも解散することができます。当然、定款は”会社の法律”のようなもののため、法的にも認められます。
まとめ
このように、予め定款にて解散事由を定めておくことは、メリットがあり、万が一の時の保険ともなります。もし、これから、株式会社を設立する方がおりましたら、このあたりについては慎重に決定することをおすすめします。
尚、解散事由は会社設立時に定款という会社のルールに含めることができますが、どんな事由であれ、解散の手続きは適正に、慎重に進めていく必要があります。株主総会、債権者集会などにおける承認をしっかり得た上で、解散登記、債務処理などの適正な処理を進めていきましょう。